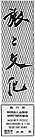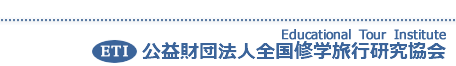| 号数 |
発行
年月日 |
主な出来事(標題) |
PDF |
| 133 |
昭和48年
1月10日
(1973年)
|
-
 - ・輝く新春を迎う
- :創造性豊かに(文部大臣 奥野誠亮氏)
:国土開発に努力を(運輸大臣 新谷寅三郎氏)
:第2世紀迎う(国鉄総裁 磯崎叡氏)
- ・風紋
-
 - ・新年を迎えて
- :みのり多い73年を(全修協理事長 山本種一)
- :情緒養成のために(全国連合小学校長会長 加藤嘉男氏)
- :本然の姿いかして(全日本中学校長会長 野沢登美男氏)
- :楽しい修学旅行に(全国高等学校長協会長 土肥輝雄氏)
- :修学旅行と教育と
- (日本教職員組合中央執行委員長 槙枝元文氏)
- :別枠で付添旅費を
- (日本高等学校教職員組合中央執行委員長 小森秀三氏)
- :日日新面目に(全修協新潟県支部長 小島要)
-
 - ・新年を迎えて
- :人間育成の機会を
- (近畿修学旅行委員会委員長 久保田八郎氏)
- :躍進の年としたい
- (関東地区中学校修学旅行委員会会長 高橋俊麿氏)
- :修学旅行は公費で
- (東海三県修学旅行委員会・列車編成委員会委員長 桜井敬一氏)
- :自然を求める旅へ
- (あおぞら号近畿地区運営協議会会長 乾英三郎氏)
- ・第14回通常総会開く 全修協 2月22・23日熱海で
・春秋で解消へ 関修委 来年度の新幹線輸送
・全修協神奈川県支部長 沢田三郎氏 逝去
・全修協初代事務局長 佐藤哲衛氏 逝去
-
 - ・新年を迎えて
- :教育界へ貢献(全修協秋田県支部長 高橋堯)
:感銘得る旅行(静岡県教職員互助組合事務局長 菅原孝氏)
:牛にあやかる(全修協宮崎県支部長 田尻貴)
:人間形成の場(全修協大阪支部長 西岡権治郎)
:がんばりの年(青森県教育厚生会専務理事 伊藤喜蔵氏)
:退職者組織を(全修協京都支部長 糸井一)
:新時代の研旅(島根県学生協常務理事 山本亮氏)
- ・近江路散歩 [4] 湖東の文化財めぐり
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 134 |
昭和48年
2月10日
(1973年)
|
-
 - ・修学旅行費の補助拡大 へき地(3級以上)全域に
- :本年度から国が2/3、市町村1/3 / 全修協運動に成果
- ・教育水準の向上へ 高度へき地の修学旅行費補助
- (文部省初中局財務課・文部事務官 松隈茂喜氏)
- ・中学生 8,900円に 48年度 要保護の補助決る
・熊本県主催で懇談会(東京渋谷)修旅で意見を交換
・全修協 第14回通常総会開く 2月22・23日熱海で
・全修協広島県支部長 大西八郎氏 逝去
・風紋
-
 - ・ことしの抱負
- :さまざまな旅(全修協愛媛県支部長 仙波勉)
:学究的に向上(全修協島根県支部長 相墨登一郎)
:旅のこころ(福岡県教職員互助会事務局長 森田則一氏)
:研旅の“三徳”(新潟県教職員厚生財団常務理事 徳橋新次氏)
- ・研修旅行 春の3コース
- 「四国」「九州」に「南近江と飛鳥」も加え 研修行事も充実
- :沖縄研修旅行に参加して (鹿児島県加治木町 伊達スミ氏)
-
 - ・来年度・近畿の修学旅行 信州コース激増へ
- 遂に10万人突破 近修委希望調査まとまる
- ・さかんな新・増築 各地の修学旅行宿舎
・さるびあ丸就航 東海汽船 東京−伊豆大島に
・ことしの抱負
- :ウシの歩みで(全修協佐賀県支部長 菊池武貞)
:真価発揮の時(全修協大分県支部長 貞池富夫)
:足もとを開拓(全修協三重県支部長 西山文男)
:理解と協力を(全修協兵庫県支部長 魚谷時太郎)
:旅と日本民族(全修協東京都支部長 青山良道)
:研旅の多様化(全修協長崎県支部長 田崎辰夫)
- ・全福協 第2回理事会 教職員福祉厚生運動を報告
・写真コンクール北海道知事賞 中野・山田両氏に
-
 - ・関修委現地研修同行記 琵琶湖、京都、吉野をめぐって
- (浦和市白幡中学校長 佐々木公彦氏)
- :修学旅行に転換期
- ・近江路散歩 [5] 湖北路は戦国の史跡
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
- ・郷土の玩具 伝統うけつぐ素朴さ 信州と飛騨
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 135 |
昭和48年
3月10日
(1973年)
|
-
 - ・全修協通常総会開く 同志の決意も堅く 第2期の目標達成へ
- :機構整備、前進へ 山本理事長の挨拶から
- ・風紋
-
 - ・総会グラフ 地区会議で検討
・全修協第34回役員会開く 特別委員会の設置へ
- 運動展開に協力布陣
- ・特別委活動に期待 解説
・さかんな船づくり 旅の海洋時代を迎う
- :新さくら丸誕生 大島運輸 東京−沖縄航路に
:「すみよし」も就航 名門カーフェリー
:「さんふらわあ5」 日本高速フェリーで完成
:おりおん丸も 大洋フェリー 大阪と北九州(苅田)に就航
- ・観光事情の説明会 愛知県の主催で開く(新宿小田急百貨店)
・スライド「古墳」 奈良歴史教室で上映
-
 - ・国鉄の値上げ反対 修学旅行界で陳情
- 現行で据置を “実施に支障がでる”と
- :陳情書
- 全修協、三地区修旅連絡協、関修委、近修委、東海三県修旅委
- ・“付添い旅費”確立へ 全修協など運動展開
・49年度あおぞら号近畿地区 8万5千余名運ぶ
・三地区修旅連絡協で第三回協議会開く
・人員超過で再調整 関修委運営委できめる
・東海三県の編成委 名称を変更「東海三県中学校修学旅行委員会」
-
 - ・夏の教職員研修旅行募集はじまる
- 17コースで実施へ「海外教育事情視察」も
- ・近江路散歩 [6] 史跡も豊かな湖西路
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 136 |
昭和48年
4月10日
(1973年)
|
-
 - ・三地区連絡協ひらく 理論と実践を推進 新コース、輸送打開も
・2県支部長が就任 神奈川県 大庭和夫氏、福島県 佐々木二郎氏
・全修協高知県前支部長 中沢義之氏 死去
・春の研修旅行 好天に恵まれ 3コース無事終わる
・風紋
-
 - ・研修旅行募集はじまる
- 研究行事がいっぱい 締切り前満員のコースも
-
 - ・ご苦労さま 半生を修学旅行に
- 大任はたして千葉柏中高橋校長、教壇を去る
- ・修学旅行は船でどうぞ 海運会社がハッスル フェリーも勢ぞろい
- ・わかくさ号表示板 国鉄、全修協へ寄贈
- 近く「わかば号」も大阪事務所へ
-
 - ・飛鳥断片 [1] 全国に残る地名
- 『1.飛鳥とは/2.各地の飛鳥/3.大和の飛鳥』
- (近畿日本ツーリスト株式会社常務取締役 桑原守也氏)
- ・近江路散歩 [7] 詩情ただよう琵琶湖
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
- ・集印帖 南禅寺・勧修寺
・史跡めぐりは自転車で 近鉄沿線にレンタサイクル
・宿泊料金を改正 オリンピック記念青少年総合センター
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 137 |
昭和48年
5月10日
(1973年)
|
-
 - ・“新幹線をふやして” 名古屋市の中学校
- 修学旅行の調査から 富士五合目に人気
- :目的地・校数と利用列車/印象深かった見学個所/
持参するおやつとその費用/カメラと時計は/旅行費はいくら
:ゆとりある日程で 学校の意見
旅行先・日程/旅館について/交通について
- ・論点 快適な修学旅行を〜実態調査結果をかえりみて〜
- (名古屋市中学校修学旅行委員会委員長 横山正氏)
- ・風紋
-
 - ・ことしも研修旅行へ 海外ふくめ18コース 満員近し、申込はお早く
・第10回東京私学現地研修会 美濃路の探究
・筑紫野(俳句)(春の研修旅行西九州コース参加者 中野つた子氏)
-
 - ・来年度の修学旅行輸送計画きまる
- 関東、信州へ19万名(近畿)東海は「こまどり」併用
- :関東地区 近畿地区 東海地区
- ・一部の学校は延期 交通ゼネストに対処
・本年度の役員決る 埼玉県修旅委
・第62回運営委開く 関東地区修旅委で
・教育一途に生きた故中沢義之氏の信念
-
 - ・飛鳥断片 [2] 古墳奇石の群れ 『4.石造遺物』
- (近畿日本ツーリスト株式会社常務取締役 桑原守也氏)
- ・近江路散歩 [8] 歴史いろどる山と峠
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
- ・郷土の玩具 素朴に故事を生かす 獅子頭など
- ・団体拝観料 京都の社寺値上げも
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 138 |
昭和48年
6月10日
(1973年)
|
-
 - ・付添旅費を別枠に 北海道教委 本年は1億8千万円
- ・7千名が増加 49年度 関東地区の新幹線利用
- ・河野正夫理事逝く
- 全修協運動に功績残して 昔を語る友いまはなく 山本種一氏談
- ・全修協新潟県支部長に徳橋新次氏が就任
- ・三地区連絡協開く
- ・風紋
-
 - ・研修旅行の申込殺到 緑と水をもとめて 魅力あふれる各コース
・アルバムひろげて
- 全修協東京都支部主催で 研修旅行思い出を語る会
- ・阿蘇(俳句)(春の研修旅行九州コース参加者 吉田アヤ子氏)
-
 - ・関修委運営委ひらく 新会長に佐藤武男氏
・枠の拡大を検討 へき地補助金8月末までに結論 文部省
・3年間の実態調査 東京私学修旅研究調査会で
・新さくら丸誕生 大島運輸 東京−沖縄間に
・わかば号の表示板 役目終えて全修協へ
・大和路を語る会 九州の高校対象に
・東京−小倉に就航 東九フェリーの「とね」
・氷川丸が資料館に ホテル営業振るわず
・回転椅子 郷土料理
・集印帖 三宝印・金地院
-
 - ・飛鳥断片 [3] 謎の多い石造物 『4.石造遺物(つづき)』
- (近畿日本ツーリスト株式会社常務取締役 桑原守也氏)
- ・補助活動進む 京都市文化観光資源保護財団 目標達成も間近か
- ・近江路散歩 [9] 暮らしを支えた産業
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
- ・郷土の玩具 いまなお民衆のなかに 木うそなど
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 139 |
昭和48年
7月10日
(1973年)
|
-
 - ・青森県 修学旅行基準を改正
- 小・中学校は1泊増 6年ぶり現場の要望とおる
- ・東海三県中学校修旅委 中山氏が委員長に
- ・第四回三地区連絡協ひらく 現場感覚注入へ
- ・風紋
-
 - ・研修旅行いよいよ開幕へ 7月21日に第1陣 光を求めて6千名が
- ・住居の誕生(国学院大学教授 樋口清之氏)
- 大和文化会の6月例会の後援から
-
 - ・修旅列車を優先運転 関修委運営委で報告
- ・栃木県中学校修旅部会総会
- 新部長に伊藤守氏 新幹線専用列車増設を要望
- ・兵庫県修旅委開く 斎藤武人委員長を再任
- ・全教互第24回総会 田畑会長を再選
- ・全修協青森県支部役員総会 強力に事業推進
- ・車はふえてもガイドが不足 三地区修旅連絡協で検討された意見
- ・本(修学旅行ガイド「秋田」県政、文化財などを解説)
- ・富士観光開発会社でロッジ新館が完成(富士緑の休暇村)
-
 - ・箸墓考 [上] 神話の中の古墳(全修協事務局長 白滝末紀)
- ・近江路散歩 [10] 風土に育つ豊かな味
- (能登川高校教諭 渡辺守順氏)
- ・郷土の玩具 農事の信仰に一と役 ワラ馬など
- ・民族学博物館 51年、万博敷地跡に
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 特集 |
昭和48年
7月10日
(1973年)
139号
とじこみ
研修旅
行ガイド |
-
 - ・48年夏教職員研修旅行ガイド
・ご参加の皆さまへ:全修協研修旅行実施本部長
・ご注意など 集合について
・集合場所案内図 研修旅行問合わせ先一覧表
-
 - ・写真コンクール ふるってご応募を
- 北海道観光連盟賞も 知事賞に花添える
- ・連絡本部旅館一覧
-
|
- 1、2頁
  |
| 140 |
昭和48年
8月10日
(1973年)
|
-
 - ・修学旅行の実態調査 東京の私立高校
- :九州方面が圧倒的 輸送にフェリーも登場
- :余裕のある三月に/奈良コースも漸増/飛行機の利用校も
- :修学旅行実施の有無、実施学年 実施時期、目的地、日程、
交通機関、旅行費、学校側意見
- ・緑の学校研究会(都内) 長野県の主催で
- ・風紋
-
 - ・夏の研修旅行終了へ 緑を満喫した6千名
- 18コースで快適な旅 写真コンクール
- ・日本海博ひらく 北陸の夢を展示 金沢市
- ・大和文化会 秋の史跡見学旅行 近江・奈良大和路へ
-
 - ・近畿二府四県修旅委で久保田委員長再選
- ・付添旅費は枠外で 埼玉県修旅委が運動
- ・滋賀県 二泊三日の中学校用モデルコースを
- ・歴史・技術を組合わせ 新コース鈴鹿と古都を結ぶ(ホンダランド)
- ・男鹿国定公園誕生 5月15日 41番目の国定公園
-
 - ・箸墓考 [下] 古代の謎を推理する(全修協事務局長 白滝末紀)
- ・修学旅行のスポット 江戸城の名残り 皇居東御苑
- ・郷土の玩具 簡素な笹野彫と赤べこ 東北地方
- ・“お白石持”の行事 伊勢神宮遷宮祭を前に
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 141 |
昭和48年
9月10日
(1973年)
|
-
 - ・へき地への拡大は見送り
- :49年度修学旅行の補助金要求 中学生1万700円に
- ・ 専用列車の増設を
- :乗りつぎも円滑に/関修委が国鉄に要望/難点は通勤時運転
- ・千葉県修旅委の役員 山形氏が委員長に
- ・風紋
-
 - ・研修旅行に参加して アイヌの実態を知る 北海道一周コース
- (青森県教育厚生会福祉課長 鈴木広氏)
- ・四国紀行(研修旅行 四国一周コース参加者 伊藤亀雄氏)
- ・研修旅行アルバム
- ・みちのく(研修旅行 東北一周コース参加者 本多芙佐子氏)
- ・四国路(研修旅行 四国一周コース参加者 伊藤孝太郎氏)
- ・下中記念財団で300万円の助成金
-
 - ・近修委で希望コースを調査 中国地方加え
- 50年度信州地区は飽和状態
- ・静岡のフィールドワーク(1) 新教材を授業に活用
- (静岡大学教授 岩橋徹氏)
- ・郷土の玩具 木彫りから練りものへ 吉良の赤馬
- ・科学技術館で入館料を改訂 来年4月から実施
-
 - ・[文化] 豊かな海との協調 沖縄国際海洋博覧会
- :船のクラスター 科学/技術のクラスター 民俗/
- 歴史のクラスター
- :魚のクラスター/アクアポリス(竜宮城の現代版 輝く五彩の光)
- ・海の無い県に海神社 奈良・近鉄沿線に2社も
- ・海人族進出の名残り
- (近畿日本ツーリスト株式会社 常務取締役 桑原守也氏)
- ・展望車 バイコロジー(国鉄・広報部提供)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 142 |
昭和48年
10月10日
(1973年)
|
-
 - ・望ましい修学旅行座談会[1] 生涯教育の一環に
- 東京都中学校の実践にきく
- ・修学旅行向上のために/人間づくりに貢献/綿密な指導体系を
- ・風紋
-
 - ・研修旅行 思い出も新たに“旅の心”を語る会
・アイヌ問題に惹かれる(北海道研修旅行参加者 千々岩敏子氏)
・ゆく雲(研修旅行立山木曽飛騨コース参加者 吉成石汀氏)
- ・アジア歴史の旅[上] 韓国の遺跡をさぐる
- (全修協茨城県支部長 永井熙)
- ・風雪に耐える石仏群 遺物は興亡の哀感を秘めて
-
 - ・中国方面に131校 近修委で希望コース調査
- :信州の混雑は解消へ 50年度列車編成を国鉄へ申請
- ・公費負担など検討 岐阜で三地区連絡協開く
- ・大阪府教互で創立25周年式典
- ・関修委で第66回運営委開く
- ・全修協各支部で反省会 研旅に貴重な資料
- ・静岡のフィールドワーク[2] 富士山の成立を追及
- (静岡大学教授 岩橋徹氏)
-
 - ・[文化] 多胡碑 みなぎる未完の美 新郡制の喜び伝う
- (全修協広報部長 早川泰雄)
- ・仏との出会い 親鸞における法悦の世界
- (兵庫県広原寺住職 村上高信氏)
- ・三重の円空 珍しい三尊像も現存
- (近畿日本ツーリスト株式会社常務取締役 桑原守也氏)
- :一宿一飯のお礼に刻んだ
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 143 |
昭和48年
11月10日
(1973年)
|
-
 - ・望ましい修学旅行座談会[2] 東京・中学校の実践にきく
- :計画は全校を挙げて/ふえる現地の分散型
- ・風紋
-
 - ・研修旅行写真コンクール 推薦作品には高野氏
- :北海道知事賞 北海道観光連盟賞他 総評
- ・研修旅行の作品 山陰の旅(三島市南田町 井上酉三氏)
-
 - ・第5回三地区修旅委連絡協で 積極策を進める
- :費用の軽減から/50年度 輸送力確保も重点に
- ・あおぞら号近畿地区運営協議会 乾会長を再選
- ・第66回関修委運営委で 輸送の最終案検討
・静岡のフィールドワーク[3] 目前に大自然の驚異
- (静岡大学教授 岩橋徹氏)
-
 - ・[文化] アジア歴史の旅(中) 韓国の遺跡をさぐる
- (全修協茨城県支部長 永井熙)
- :古都も並木のかげに 点在する王稜や寺院はひっそりと
- ・寺内町・発展の歴史
- (近畿日本ツーリスト株式会社常務取締役 桑原守也氏)
- :自由都市の面影残る 富田林と今井に旧家の遺構
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 144 |
昭和48年
12月10日
(1973年)
|
-
 - ・望ましい修学旅行座談会[3] 東京・中学校の実践にきく
- :分散には条件が必要 雨天の場合も考えよう/畳数も料金次第
- ・風紋
-
 - ・補助金に続き職専免(福島県) 研修旅行の公共性認め
・[旅] 来年の研修旅行決る 3季で25コース設定
- 第17年次迎え内容充実
- :特別研修コース/夏季コース/第11次海外教育視察団
-
 - ・関修委と国鉄が協議 50年度計画は流動的
- :社会情勢もからんで 専用列車1本の原則守る
:日光コースが増加 名古屋市修旅委実態調査でわかる
- ・滋賀県 来年7月に湖西線開通 修学旅行誘致に拍車
- ・思い出の植樹 富士緑の休暇村で修学旅行生たち
・関修委の運営委 12月20日午前11時から東京都教育会館で開く
・奈良県主催の“大和路を語る会”は1月20日 茨城県水戸市で開く
-
 - ・[文化] 修学旅行の作文 流動する東京
- (名古屋市立御田中学校3年 落合いずみさん)
- ・残照に浮かぶ武蔵野 埼玉・平林寺 落葉の小路は冬枯れて
・アジア歴史の旅 [下] 韓国の遺跡をさぐる
- (全修協茨城県支部長 永井熙)
- :出土品で飾る博物館 神鐘にまつわる少女の悲話も
- ・[本] 樋口清之著「日本史再発見」 歴史にふれる手掛りに
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 145 |
昭和49年
1月10日
(1974年)
|
-
 - ・輝く新春を迎う
- :人間育成のために(文部大臣 奥野誠亮氏)
:輸送確保に全力を(運輸大臣 徳永正利氏)
:安全第一主義で(国鉄総裁 藤井松太郎氏)
- ・風紋
-

- ・新年を迎えて
:修学旅行も転換期(全修協理事長 山本種一)
:真価を発揮する時(全国連合小学校長会長 小山昌一氏)
:教育的意義見直す(全日本中学校長会長 片寄八千雄氏)
:適切な生徒指導を(全国高等学校長協会長 土肥輝雄氏)
:難局のり越えよう(日本教職員組合中央執行委員長 槙枝元文氏)
:豊かな修学旅行に
- (日本高等学校教職員組合中央執行委員長 小森秀三氏)
- :こころ豊かに(全修協兵庫県支部長 魚谷時太郎)
- :使命発揮の年(全修協大阪支部長 西岡権治郎)
- 山口県支部長 開地茂行)
-
 - ・新年を迎えて
- :国土への愛を(全修協理事・北海道支部長 高田治郎)
:初心にかえる(全修協新潟県支部長 徳橋新次)
:高い運動評価(全修協中央研修部幹事 伊藤喜蔵)
:事業の前進を(全修協宮崎県支部長 田尻貴)
:期待の団体に(全修協中央研修部幹事 中島欣一)
:旅を味わおう(全修協愛媛県支部長 仙波勉)
:難関克服して(全修協理事・山形県支部長 完戸一郎)
:実力の発揮へ(全修協三重県支部長 西山文男)
:同志とともに(全修協徳島県支部長 近藤清)
:地道な運動で(全修協中央研修部幹事 貞池富夫)
:中南米までも(全修協監事 芦田重左衛門)
-
 -
- ・新年を迎えて
- :生きた勉強に(全修協秋田県支部長 高橋堯)
:目的ある旅を(全修協東京都支部長 青山良道)
:旅のモラルを(全修協理事 岡本仁)
:価値高い旅行(全修協山口県支部長 開地茂行)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 146 |
昭和49年
2月10日
(1974年)
|
-
 - ・望ましい修学旅行座談会 [4] 東京都中学校の実践にきく
- :問題抱える遠隔校/バスガイド不要か/代休のやりくりも
- ・風紋
-
 - ・全修協総会ひらく(2月7・8日)積極策の推進誓う
・研修旅行募集始まる 3月下旬3コースで 特別研修も加えて実施
・冬の研修旅行終る 北海道地区
-
 - ・第7回関修委研究集会開く 人とのつながり協調
- :中学校の修学旅行原点に戻そう
- ・第6回関修委運営委ひらく
・東海三県中学校修旅委が業界と懇談会 直前の値上げ困る
- :旅館の接遇に論議集中
- :バス協会 燃料確保運動を
-
 - ・[文化] 研修旅行の作品 山陰の旅(井上酉三)
・札幌 屯田兵の建物 史跡に衣がえ
・歴史の道 [1] 絹の道
- 明治の財政を支える 異人館や生糸豪商の屋敷あとも
(郷土史家 三浦富雄氏)
- ・郷土の玩具 面白いおめでたづくし 香川の嫁入人形
- ・人類の英知あつめて 花ひらく万国博
- :進歩と調和と 全会場にあふれるテーマ
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 147 |
昭和49年
3月10日
(1974年)
|
-
 - ・第15回全修協総会開く 総力あげ運動展開へ 出席の全員が誓いあう
- :不屈の精神で前進(全修協理事長 山本種一)挨拶要旨
- ・風紋
-
 - ・望ましい修学旅行座談会[5] 東京都中学校の実践に聞く
- :分散型は全国的傾向
- ・古代への思慕を−仁徳陵随想−
- (全修協常務理事・事務局長 白滝末紀)
|
- 1、2頁
  |
| 148 |
昭和49年
4月10日
(1974年)
|
-
 - ・望ましい修学旅行座談会 [5] 東京都・中学校の実践に聞く
- :疲労度違う新幹線 無駄な時間が多い
- ・風紋
 - ・春の研修旅行終わる 好評うけた各コース
- 参加者の声“学年末を有意義に”
- :西九州コース、沖縄・石垣コース、
- 難波・飛鳥・大和の古文化探究コース
- ・歴史の道[2] 絹の道
- 石垣に繁栄しのぶ鉄道開通で人通りもなくなって
-
|
- 1、2頁
  |
| 149 |
昭和49年
5月10日
(1974年)
|
-
 - ・別枠付添い旅費獲得
- 本年度は3,000万円 埼玉県修旅委の運動みのる
- :一人当り約7,000円 これを突破口にして
- ・北海道教委で基準改正 距離制に切りかえ
・東海三県の中学校で 来年度輸送計画きまる
・近畿二府四県修旅委 新役員の顔ぶれ
・風紋

- ・夏の研修旅行 精選コース勢揃い 申込はお早く
・歴史の道(3)絹の道 黙して語らぬ石の垣 やがて桑の木は根こそぎに
- (郷土史家 三浦富雄氏)
-
|
- 1、2頁
  |
| 150 |
昭和49年
6月10日
(1974年)
|
-
 - ・本年度 要保護の修旅補助金
- 中学生1万100円に へき地も同額 小学生は3,400円
- ・三地区修旅連絡協開く 組織あげ実態調査
・本年度の近修委 新委員の顔ぶれ
・「修学旅行のための大和路を語る会」秋田・山形・福島で
・風紋
-
 ・修学旅行生に安眠を 東京本郷消防署 人命守る裏方さん
・ぶらじる丸が鳥羽で教育施設に
・教職員の研修旅行7月6日まで受付中
・高松塚古墳 壁画の意味するもの−模写の一般公開に寄せて−
- (関西大学教授 網干善教氏)
-
|
- 1、2頁
  |
号外 |
昭和49年
7月5日
(1974年)
第16回
研修旅行版 |
-
 ・第16回研修旅行はじまる 光と緑を求めて 出発日と出発時刻
・ご参加の皆さまへ(全修協研修旅行実施本部長 白滝末紀)
・研修旅行問合わせ先一覧表
-
 - ・集合場所案内図
- ・連絡本部旅館一覧
-
|
- 1、2頁
  |
| 151 |
昭和49年
7月10日
(1974年)
|
-
 -
・修学旅行補助金制度ひろがる 倍増や校外活動にも
- :東京 秋川、羽村、立川など
- ・関修委総会ひらく 活動目標を決定
・風紋
-
 - ・最高の成績おさめて 研修旅行はじまる 教職員六千余名が参加
- ・研修旅行写真コンクール 北海道コース 知事賞、道観連賞も
- ・集印帖 中尊寺、毛越寺
- ・横顔 愛される人柄で 全修協青森県支部長
-
 -
・近修委 輸送計画まとまる 関東など3コースで
- :50年度656校の168,000名
- ・岡山県の修学旅行 ほとんどが九州へ 本年から専用列車運転
- ・台風8号・新幹線の運転中止 応急措置で全員運ぶ
- :修学旅行 栃木県23校が影響 延期校の日程決る
- ・別館・比叡が8月1日開業 延暦寺会館
- ・さっぽろ丸が八月から就航 日本沿海フェリー
-
 -
・夏を色どる風物詩 京都の祭り(11箇所)
- ・歴史の道[4] 絹の道 新河岸川 早船で運ぶ江戸の味
- (郷土史家 三浦富雄氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 152 |
昭和49年
8月10日
(1974年)
|
-
 - ・栃木県 修旅部会の総会開く 強力な事業計画決る
- :部長に伊藤守氏が再選
- ・本年度の教育予算 千葉県修旅委で検討
- ・風紋
-
 - ・特集 湖西線が開通 琵琶湖に沿って74キロ 周辺に豊富な文化財
- :ポイントは比叡山 山頂に自然の公園
- 琵琶湖八景 近江八景 味覚と特産品
- :滋賀県修学旅行誘致促進協議会
-
 - ・あおぞら号 50年度の輸送計画
- :伊勢へ85,000名 近畿地区運営協で決定
- ・教育理論たてよう(栃木県中学校修学旅行部長 伊藤守氏)
- ・修旅委をふりかえる
- :教師全部が考えよ(前近畿修学旅行委員長 久保田八郎氏)
- :意義深める運動へ(前茨城県中学校修旅委員長 介川容介氏)
- ・さっぽろ丸が就航 日本沿海フェリー 東京−苫小牧間に
-
-
 - ・研修旅行の作品
- :鮎の宿(俳句10篇)
- (研修旅行 木曽立山飛騨コース参加者 秋吉良子氏)
- :さいはての旅(俳句8篇)
- (研修旅行 北海道一周コース参加者 山田操氏)
- ・古代の群馬を探る[1] 端緒をひらいた岩宿
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 153 |
昭和49年
9月10日
(1974年)
|
-
 - ・修学旅行の補助金要求 文部省
- :中学生14,400円要保護 50年度 へき地は特殊性考慮して
- ・全修協の実態調査から[1]
- :値上げ攻勢続く 修学旅行 父兄負担も重く
- ・全修協栃木県支部長 北条虎雄氏 死去 全修協運動に功績残す
- ・風紋
-
 - ・研修旅行の作品
- :家族で楽しんだ研修旅行[1] 洞爺湖でボートも
- (研修旅行北海道コース参加者 中西道子氏)
- :殉教の地に立って 目をおおう原爆資料[上]
- (研修旅行九州一周コース参加者 山田永子氏)
- :北海道の旅[短歌8篇]
- (研修旅行北海道一周コース参加者 藤原美代子氏)
- ・郷土の玩具 素朴な姿の紙づくり 浜松・紙凧 松江・人形
-
 - ・都立神代高校の体験実習
- :弘前市農協で受入れ リンゴ収穫の作業を
- ・修学旅行の基準調査 本年度も全修協で
- ・関東・東海・近畿 近く第7回連絡協
- ・来年度の関東地区中学校 新幹線で関西へ572校 11万4千名を運ぶ
- ・車イスの修学旅行
- ・スクール・メイト・バス 京都市内で運行
- :自由時間を活用 高校修学旅行に新企画
- ・三重県公立学校職員互助会 設立20周年の式典
- ・東京−松阪 航路ひらく 10月17日からフジフェリー
-
 - ・古代の群馬を探る[2] 価値高い土偶の発見
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- ・期待される沖縄国際海洋博 来年7月20日から開催
- :海上に浮かぶ都市も
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 154 |
昭和49年
10月10日
(1974年)
|
-
 - ・全修協の実態調査から[2]
- :物価狂乱ひしひしと 修学旅行2年間に倍額の例も
- ・時論 修学旅行シーズンを終えて[1] 集団暴力事件を憂う
- (全修協研究調査部長 岩崎武夫)
- ・風紋
-
 - ・ことしの研修旅行アンケートから[1]
- :北海道A、北海道B、知床・納沙布、利尻・礼文島コース
- :飛行機の利用は満点 講演も有意義だった
- ・研修旅行の作品
- :美しく雄大な山なみ にえたぎる火口へ[中]
- (研修旅行九州一周コース参加者 山田永子氏)
- :開拓者の苦労も知って[2] 魅せられた層雲峡
- (研修旅行北海道コース参加者 中西道子氏)
- :北海道の旅[短歌7篇]
- (研修旅行北海道一周コース参加者 藤原美代子氏)
-
 - ・仲よし修学旅行 鴎友学園中学校 山村の子どもと交歓
- :来年は10回目岩手県の柳沢校へ
- ・関修委 基本調査を実施 12月には現地研修会
- ・全修協の研修旅行 6,000名突破へ 史上二回目の好成績
- ・[本]
- :「新幹線当世膝栗毛」 時計に合わせる新旅行案内
- :「修学旅行のしおり」 九州各県を平易に解説
- ・ホンダ・ランド本社移転
-
 - ・古代の群馬を探る[3] 縄文期の気候と住居
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- ・17人の修学旅行 団体割引なし(上野動物園・国立博物館)
- ・京都市内の寺院で 庭園など特別公開
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 155 |
昭和49年
11月10日
(1974年)
|
-
 - ・修学旅行 三地区連絡協が調査 現実の姿をとらえる
- ・時論 修学旅行シーズンを終えて[2] 集団暴力事件を憂う
- (全修協研究調査部長 岩崎武夫)
- ・風紋
-
 - ・研修旅行写真コンクール 推薦作品には大鹿氏
- :北海道知事賞 北海道観光連盟賞他 総評
- ・ことしの研修旅行アンケートから[2]
- :東北一周、陸中海岸、佐渡・磐梯、木曽・立山・飛騨コース
- :部屋割りは良い 研修行事をふやして
-
 - ・修学旅行専用列車のダイヤ 決定発表は年末に
- :国鉄本社50年度春季 総合的な検討重ねる 万全を期した上で
- ・全修協の実態調査から[3]
- :軒なみアップ 中学校の修学旅行 香川、愛媛、宮崎、熊本県
- ・中国展におもう[1] 逞しく伸びる生産(全修協事務局長 白滝末紀)
- ・郷土の玩具 伝説と風習を象徴 東京・みみずく 長崎・子泣相撲
-
 - ・古代の群馬を探る[4] 貴重な樽式土器発見
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- ・研修旅行の作品
- :来年もぜひ研修旅行に[3] 岩と滝のある風景
- (研修旅行北海道コース参加者 中西道子氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 156 |
昭和49年
12月10日
(1974年)
|
-
 - ・51年度の基本計画 コースは3方面に 近修委が方針打ち出す
- ・茨城県中学校修学旅行委員会
- 組織の強化策など協議会で検討重ねる
- ・あおぞら号近畿地区協 51年の計画検討 役員も選出
- ・三地区修学旅行の実態調査 来年一月に発表
- ・関修委現地研修会実施
- ・関修委で12月10日に運営委員会開く
- ・つなぎ列車の確保 栃木県が国鉄に要請
- ・風紋
-
 - ・来年の研修旅行 19回迎えて新構想
- :意義深い特別研修も 3季制 海外を含めて30コース
- :出発と会費・日程[1]
- :研修旅行特別委で誓い合う 1万名突破へ総力
-
 - ・29年ぶりの修学旅行 名古屋明治小のOBたち 在校生といっしょに
- ・12月から法隆寺で拝観料改正
- ・中国展に思う[2] 美の極致示す工芸(全修協事務局長 白滝末紀)
-
 - ・[本] 「教育会館物語」 克明な県教育史(青森県)
- ・古代の群馬を探る[5] 布を織る機会も出現
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 157 |
昭和50年
1月10日
(1975年)
|
-
 - ・輝く新春を迎う
- :人間回復の絶好機(文部大臣 永井道雄氏)
- :交通公害の防止策(運輸大臣 木村睦男氏)
- ・風紋
-
 - ・新年を迎えて
- :先ず安全対策から(国鉄総裁 藤井松太郎氏)
- :新しい年の課題と取り組もう(全修協理事長山本種一)
- :共に学ぶ修学旅行(全国高等学校長協会会長 成田喜澄氏)
- :洗い直しを図ろう(全日本中学校長会会長 片寄八千雄氏)
- :修学旅行は公費で
- (日本教職員組合中央執行委員長 槙枝元文氏)
- :国土愛の修学旅行
- (関東・東海・近畿三地区公立中学校修学旅行連絡協議会会長 中山正秋氏)
-
 - ・新春を迎えて
- :楽しい修旅を(全修協大阪支部長 西岡権治郎)
:計画に配慮を(全修協愛媛県支部長 仙波勉)
:寿修学旅行も(全修協青森県支部事務局長 伊藤喜蔵)
:サービス強化(大分県教職員互助会事務局長 広畑博氏)
:風雪にたえて(全修協宮崎県支部長 田尻貴)
:課題を明確に(全修協秋田県支部長 高橋堯)
:諸特典の活用(山形県教職員互助会事務局長 酒井充氏)
:冬の北海道へ(全修協理事・北海道支部長 高田治郎)
:昔の研修旅行(和歌山県教育互助会事務局長 阪上広雄氏)
:参加者の共感(全修協新潟県支部長 徳橋新次)
:暖かい奉仕を(大阪府教職員互助組合常務理事 中島欣一氏)
-
 - ・新春を迎えて
- :水準を高めて(大阪府教職員互助組合事務局次長 神代義秀氏)
:中国へ行こう(全修協山形県支部長 完戸一郎)
:新時代の旅行(新潟県教職員厚生財団常務理事 笹川正人氏)
:遠隔地対策も(青森県教育厚生会福祉課長 鈴木広氏)
:新制度の活用(全修協三重県支部長 西山文男)
:専用の宿舎を(近畿二府四県修学旅行委員会委員長 北牧一雄氏)
:児童の交流も(あおぞら号近畿地区運営協議会会長 乾英三郎氏)
:苦難のり越え(関東地区中学校修学旅行委員会会長 佐藤武男氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 158 |
昭和50年
2月10日
(1975年)
|
-
 - ・本年度予算 要保護の修旅補助金 中学生13,500円 へき地も同額
- :小学生は4,800円
- ・父母負担の軽減 三地区協で運動方針
- ・全修協 第16回通常総会開く 3月5,6日、熱海で
- ・引率旅費の獲得へ 旅行地は関西方面が好適
- (関東地区中学校修学旅行委員会会長 佐藤武男氏)
- ・全修協栃木県支部長に梅沢茂氏が就任
- ・風紋
-
 - ・新生中国視察記[1] 衣食たりて礼節
- (全修協理事・山形県支部長 完戸一郎)
- ・研修旅行の募集開始 春季 異色の6コースで
- ・研修旅行の作品
- :心に残る九州の旅 薩摩半島も思い出の一つ[下]
- (研修旅行九州一周コース参加者 山田永子氏)
- ・自然との信頼感を 新しい年を迎えて
- (兵庫県学校厚生会理事長 白淵義雄氏)
-
 - ・専用船ご苦労さま わかば丸・ふたば丸
:老朽化で廃船 新造船を期待 運営協は強化存続へ
- 新鋭観光船で代替
- ・関修委が大宮市で研究発表会を開く
- ・ひかり号を2本に 関修委で申請きめる
- ・近修委の調査 新幹線増発を要望 四国と九州ふえる
- ・埼玉県修旅委で運動の強化を決定
-
 - ・古代の群馬を探る[6] 一万基以上の古墳が
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- :群馬県内のおもな古墳
- ・[本]
- :「梅干と日本刀」 優れた科学性日本人の知恵
- :「近畿の旅」完成 関修委監修・関東五県修旅委が編集
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 159 |
昭和50年
3月10日
(1975年)
|
-
 - ・全修協第16回通常総会開く 強力に施策の推進へ
- :全組織の活動を期待 主な事業計画
- :歴史の転換期迎う(全修協理事長 山本種一)
- ・風紋
-
 - ・新生中国視察記[2] 3年の食糧備蓄
- (全修協理事山形県支部長 完戸一郎)
- ・春の研修旅行満員 夏季コース申込みを受付中
- ・中尊寺修学旅行記 未来への文化遺産
- (秋田市立勝平小学校6年 大塚悦子さん)
-
 - ・三地区修旅連絡協開く 先ず補助金獲得を 加盟地区拡大も要望
- ・ひかり号の増発を 関修委・近修委 国鉄へ陳情
- :12万名に大幅ふえる・関東 中国と九州へ9万名・近畿
- ・修旅生にお小遣い 埼玉・騎西町で
-
 - ・古代の群馬を探る[7] 土器の母体も発掘へ
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- ・[本] 「宮崎・修学旅行のしおり」 生徒向きに好編集
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 160 |
昭和50年
4月10日
(1975年)
|
-
 - ・関修委、近修委 新幹線の増発要望 決定、微妙な段階
- :混雑時・つなぎ列車で難航 強力に要請修旅委側
- ・車内にあふれる若さ 修学旅行シーズン迎う
- ・修学旅行 九州へ初名乗り
- :近畿 新幹線延長を機に
- ・駒場東邦で修旅手引書 学習用設問に特色
- ・風紋
-
 - ・ことしも研修旅行へ 16コースで実施 夏季 教育的行事を盛って
- :特別研修コース
- 北海道 沖縄国際海洋博尾瀬の探勝 万葉史跡(筑紫路)
- 東北、四国一周、南紀・伊勢志摩コース
- ・四国路にて(短歌他)
- (研修旅行四国路コース参加者 山本利左衛門氏)
-
 - ・関修委の研究会開く
- :オリエンテーリング導入の新企画 埼玉加須北中が経験発表
- ・幻想的な旅はいかが 世界メルヘンの館 鈴鹿サーキットに建設
- ・つなぎは一般混乗 東北線、乗務員不足で
- ・運営委員会 関修委で開く
-
 - ・新生中国視察記[3] 権力下の史跡も
- (全修協理事山形県支部長 完戸一郎)
- ・古代の群馬を探る[8] 珍しい石積みの古墳
- (前群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 161 |
昭和50年
5月10日
(1975年)
|
-
 - ・国鉄スト 修学旅行列車走らず 代替策で万全
- :全修協・修旅委 呼応して二面作戦
- ・3方面へ約19万名 近修委 来年度の割当て決る
- ・来年度も混乗で 東北線 関修委でつなぎ列車対策
- ・中国九州のモデルコースを作成 近畿日本ツーリストで
- ・三地区協総会開く
- ・風紋
-
 - ・もりあがる研修旅行
- :申込み三千名突破へ 昨年より二十日も早く到達
- :多彩な17コース
- ・北海点景(俳句12篇)
- (研修旅行北海道一周Bコース参加者 田上和美氏)
-
 - ・札幌北陵高校 グループ見学に成果
- :一年かけて事前調査 貴重な資料まとまる 友情深める場にも
- :京扇子:二年二組女子、京都の味
- :二年三組男子、各ねらいとまとめ
- ・茨城県中学校修旅委開く ブロック組織確立へ
- :新委員長に吉田四郎氏 水戸市幹事会設け運営
- ・社寺の団体拝観料[1] 京都・四月から
- ・相馬市立中学校3校生徒の国鉄ストによる修旅中止への抗議文まとめ
-
 - ・富山県の文化財[1] 雷鳥伝説も多い
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
- :立山の生い立ち/立山開山の伝説/神の使い“雷鳥”/立山信仰
- と売薬/立山と国指定の文化財
- ・古代の群馬を探る[9] 上代を知る手がかり
- (前群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 162 |
昭和50年
6月10日
(1975年)
|
-
 - ・関修委の本年度総会開く 基本方針を決定 修旅の公費負担など
- :会長に海保氏就任/要保護対策も推進/本年度の役員
- :総会挨拶[要旨](会長 海保四郎氏、全修協理事長 山本種一)
- ・来年度は12万名に 東海地区 新幹線とこまどり号で
- ・風紋
-
 - ・研修旅行 全国で爆発的人気 早くも5千6百名に
- ・沖縄国際海洋博 紺ぺきの海に展開 色とりどり、出品競う
- ・全修協青森県支部で役員総会開く
- ・大和路を語る会 九州各市で開く
- ・ストで出発日変更 東海三県の修学旅行
- ・関修委の新幹線割当て 完成は七月中旬に
- ・関修委の会則[1]
-
 - ・韓国へ修学旅行 青森県の松風塾高校 友情深めた親善の旅
- :日本文化の源流も知る
- :柳・文相の招きで 同校教諭の話
- ・養護学校教諭の読売新聞投書の内容
- ・日帰りで東京湾めぐり 都観光連と東海汽船 洋上教室をひらく
- ・研究調査協力校[1]
- ・団体拝観料[2] 京都の社寺
-
 - ・古代の群馬を探る[10] 古墳の主を語る碑文
- (群馬県中学校長会長 石井清二郎氏)
- ・富山県の文化財[2] 魚津の三大奇観
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
- ・集印帖 東大寺・金剛福寺
- ・京都 七月の行事
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 163 |
昭和50年
7月10日
(1975年)
|
-
 - ・第8回三地区連絡協ひらく 本年の計画決る
- :目標を集団指導に 基本態勢の位置づけ
- :新役員きまる 会長に海保氏
- :作文集発行を計画/補助金増額運動も
- ・風紋
-
 - ・夏の研修旅行 7000名ライン突破 教育現場の支持増す
- ・全修協新潟県支部長に笹川正人氏が就任
- ・交歓つづけて10年 鴎友学園が記念の修学旅行 お土産も沢山持って
- ・本年度近修委の役員決る 委員長に粕本氏再選
-
 - ・三地区の基本調査結果 影をひそめた無用論
- :高い学習効果 意識調査
- ・青森県八戸北高校 定着した自主見学 5年目迎える新方式
-
 - ・富山県の文化財[3] 遺跡の多い氷見
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
- ・東京私学の現地研修会 日向・阿蘇と国東へ
- ・[本] 「近江の顔」シリーズ 滋賀県から発行
- ・関修委の会則[2]
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 164 |
昭和50年
8月10日
(1975年)
|
-
 - ・日中友好の旅へ出発
- :中国の招き受けて 全修協山本理事長を団長に
- ・B電車は11時12分 関東地区9時台の集約臨中止で
- :[解説] 抜本的対策が必要
- ・つなぎ電車運転要望 関修委運営委ひらく
- ・修学旅行と社会科学習[1]
- :肌で触れた京の歴史 中学生のレポートから
- (都立教育研究所指導主事 江川滉洋氏)
- ・風紋
-
 - ・ネパール紀行 文化的な匂いも
- (全修協青森県支部事務局長 伊藤喜蔵)
- ・夏の教職員研修旅行 7000名が参加 盛況のうちに終わる
-
 - ・水戸市修旅委の活動 強力な学校集団
- :学年主任で幹事会 コース 各校の特徴生かす
- ・青年の家で宿泊研修
- :新しい修学旅行実践 三重上野高校で成果あげる
- ・野生動物園が誕生 日本サファリパーク会社 宮崎県佐土原町に
- ・気象観測の特別展 科学技術館で開く
・奈良の采女祭り
-
 - ・修学旅行の作文
- :比叡山へ 北海道立札幌北高校
- :研修のねらい/研修を終えて(二年一組第四班 生徒6名)
- :京都慕情 青森県立八戸北高校(二年七組第十班 生徒4名)
- ・富山県の文化財[4] 精彩な合掌造り
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 165 |
昭和50年
9月10日
(1975年)
|
-
 - ・日本教職員友好訪華団 全修協運動に金字塔 素顔の中国で学習
- :各所で熱烈な歓迎を/三時間におよぶ座談会も
- ・修学旅行と社会科[2] 詰込み主義から脱皮 ちえの宝庫ひらくカギを
- (都立教育研究所指導主事 江川滉洋氏)
- ・風紋
-
 - ・万葉史跡・筑紫路研修旅行記 蘇える古代への回帰
- (全修協事務局長 白滝末紀)
- ・奈良・大和文華館で所蔵名品展ひらく
- ・[本] 「はるかな尾瀬」朝日新聞前橋支局編
- ・研修旅行写真コンクール お早くご応募を
- ・沖縄国際海洋博アクアポリス十万人目の入場者は研修旅行参加者
-
 - ・51年度 文部省修学旅行の補助金要求 中学生要保護14,900百円
- :へき地は大幅増額で対処
- ・関修委運営委ひらく 現地研修は京都奈良へ
- :国鉄側から来年の輸送事情説明
- ・「近畿の旅」編集委員会のメンバー
- ・枚方市長に近畿二府四県修学旅行委員長 北牧氏が当選
- ・修旅は北東北へ 首都圏の教諭招く
-
 - ・富山県の文化財[5] 武将の面影伝う
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
- ・歴史の道[5] 井の頭池(上)
- :江戸で最古の上水道 縄文期の遺跡もある水源池
- (郷土史家 三浦富雄氏)
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 166 |
昭和50年
10月10日
(1975年)
|
-
 - ・[対談] 修学旅行とモラル(上) 少年蝕ばむ社会風潮
- ・大自然にかこまれて
- :「高原千葉村」のことなど(千葉市立緑町中学校長 時田米蔵氏)
- ・東海三県中学校修旅委総会開く 安江氏が委員長に
- ・栃木県修旅委で決定 全県対象に調査を
- ・三地区協ひらく 11月14・15日、水上で
- ・風紋
-
 - ・友好訪華団の記録 全修協主催
- :徹底した産学協同(滋賀県教職員組合執行委員 中川泰治氏)
- :歴史と文化の深さ(山形県教育委員会教育長 赤星武次郎氏)
- :再見・中華朋友(北海道教職員組合調査部長 小関恒夫氏)
-
 - ・友好訪華団の記録 全修協主催 (つづき)
- :育てる高い道義心(全修協栃木県支部長 梅沢茂)
- :八億人の素顔知る(埼玉県修学旅行副委員長 多田力氏)
- :一見して百考する(全修協愛媛県支部長 仙波勉)
- ・沖縄海洋博 冬の研修旅行募集 海洋博に学生版も登場
- :海の未来もとめる 近畿日本ツーリスト ヤング・グループで
- ・春季は12コースで 全修協の研修旅行
-
 - ・富山県の文化財[6] 加賀百万五と越中 興亡の歴史綴る
- (富山県教職員厚生会業務係長 清水巌氏)
- ・歴史の道[6] 井の頭池(下)
- :弁財天信仰で栄える 徳川家康が愛飲したお茶の水
- (郷土史家 三浦富雄氏)
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 167 |
昭和50年
11月10日
(1975年)
|
-
 - ・[対談] 修学旅行とモラル(下) 引率教職員の飲酒は
- ・東京本郷の旅館街でことしも安全対策 消防署が協力
- ・10時台のひかり号 関修委で強く要望
- ・風紋
-
 - ・友好訪華団の記録 全修協主催
- :すばらしい教材に
- (東京都杉並区立松渓中学校教諭 黒崎キクヨ氏)
- :祖国建設に燃える(全修協長野県支部事務局長 田口国雄)
- :新しい中国に学ぶ(全修協三重県支部幹事 伊藤好道)
-
 - ・友好訪華団の記録 全修協主催 (つづき)
- :中国訪問あれこれ
- (秋田県学校生活協同組合専務理事 柿崎忠治氏)
- :“自由”を誇る市民(全修協熊本県支部長 村田正実)
- :教育革命の推進力(都立高島高校教諭 萱原昌二氏)
- :古くて新しい国
- (全修協兵庫県支部幹事・兵庫県議会議員 村上旭氏)
-
 - ・研修旅行写真コンクール入賞作品きまる 推薦作品には鷲見氏
- :北海道知事賞 北海道観光連盟賞他 総評
- ・51年春のコース
- ・沖縄海洋博へ 最後のチャンスです
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |
| 168 |
昭和50年
12月10日
(1975年)
|
-
 - ・全修協の研修旅行 春夏で32コース
- :一万名獲得へ 特別委、地区会議で本決り
- ・第9回三地区修旅連絡協開く
- :論文と生徒作文募集 本年度も実態調査実施
- ・結束して成果を 全修協理事長 山本種一の挨拶から
- ・風紋
-
 - ・友好訪華団の記録 全修協主催
- :人民に奉仕する心(全修協名古屋分室長 鬼頭藤松)
- :階級章のない社会(東京都教職員互助会参事 鈴木春之助氏)
- ・飛鳥と柳生 宿泊料改訂
-
 - ・近畿地区あおぞら号運営協
- :新会長に瀬尾武敏氏 各県から役員も選出
- ・「近畿の旅」を編集 関修委で改訂版完成
- ・奥志摩の賢島ロッジ 修旅生を受入れ
- ・東海三県中学校 春の輸送決る 52年度は秋型敬遠へ
- :修旅委 第二こまどり廃止
・関修委 現地研修会は中止
- ・宮崎サファリパークが開場
-
 - ・全修協春の研修旅行
- :特選12コースが登場 文化育成の風土にふれる
- :国東文化コース 臼杵に麿崖仏の粋/点在する社寺を見学
- :隠岐島コース 残照に映える岩肌/歴史的風土の研究も
- :沖縄と石垣島コース 島の生活に触れる
- :春の研修旅行コース 一般・特別研修 各コース
-
|
- 1、2頁
  -
- 3、4頁
  |